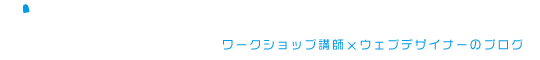ディベートの歴史を簡単に解説します。
はじめて訪問される方はこちらの記事をお読みください。
-

ディベートの基礎知識-4つの特徴-
論 ねぇ、ディベートってよく聞くけれど、実際はどんなものなの? 論 議論や討論をゲームにしたもの!って感じかな。 ディベートとは何か? 目的と効果は? やり方のコツは? この記事では、「ディベート」に ...
今回お話するのはディベートの歴史と今後です。
目次
イギリス>アメリカ>日本

Free-Photos / Pixabay
イギリスの大統領演説からスタート
ディベートの発端は、イギリスの大統領演説ですね。大統領候補者の演説をディベートの形式で行い、国民に聞かせて、どちらの政策のほうが望ましいかを議論して国民に選ばせました。
ディベートのテーマが「政策」に偏っているのは、このようなイギリス発祥の経緯があるのかもしれませんね。
アメリカがマネをした
アメリカの大統領演説でもイギリスと全く同じ形でディベートが行われるようになりました。アメリカでも大統領選のディベートがありますよね。今だとディベート=アメリカ的なイメージがあるかもしれませんが、実は後発組なんです。
後に、ハーバード大学がNDT形式というアカデミックスタイルのディベートを作り、アイビーリーグ中心に普及さてきたんですね。これがいわゆる「アカデミックディベート」です。
明治時代に日本がアメリカのディベートを取り入れた
元々、ディベートは、明治維新の前に取り入れられたといわれています。
千葉県で教職をしている方のブログが参考になったので、そのまま引用させていただきます。
ところが最近、福沢諭吉の本を読んでいて、すでに明治維新の前に、福澤はその概念がわかっていたことを知ったのです。それが次の一文。『仮令(たと)い議論をすればとて面白い議論のみをして、例えば赤穂義士の問題が出て、義士は果たして義士なるか不義士なるかと議論が始まる。(中略)やはり福沢諭吉という人は、物事の本質を突きつめる方なのだろうと思わずにはいられません。すなわち、事の是非を判断するうえで、絶対的なものなどない。どちらの見方に立つかによって、正しいかどうかというものが決められる、相対的な位置づけにある。
おそらくディベートという方法論が日本に伝わる前から、福澤はその思考訓練をすることの重要性をわかっていたのでしょう。
当時はまさに封建時代。誰の立場を尊重するかが色濃かった時代です。そんな中、福沢諭吉先生は、あらゆる人の立場に立って物事の本質を突き詰める力を養う力としてディベートを取り入れたのでしょう。あくまで思考の訓練として、そこに個人の利益を介入しないのが大きいでしょう。
今後のディベートはどうなる?
ややアカデミックディベートがガラパコス化しているというのが正直なところですね。
ディベートのような学習プラットフォームは注目されていますが、現実に運用が難しいため、上記のディベートは日本ではあまり流行らないかなと踏んでいます。但し、即興ディベートワークショップの活動を経て、ディベートは必要とされていることは参加者様の声でわかります。
この道がどこまで行くかわからない!
でも、どこから来たか!それだけはわかっている!J soul brothers 3代目 R.Y.U.S.A.I
私は、第三世代のディベーターとして、この情報化社会で皆さんのお役に立てる学習プラットフォームを作っていくだけですよ。